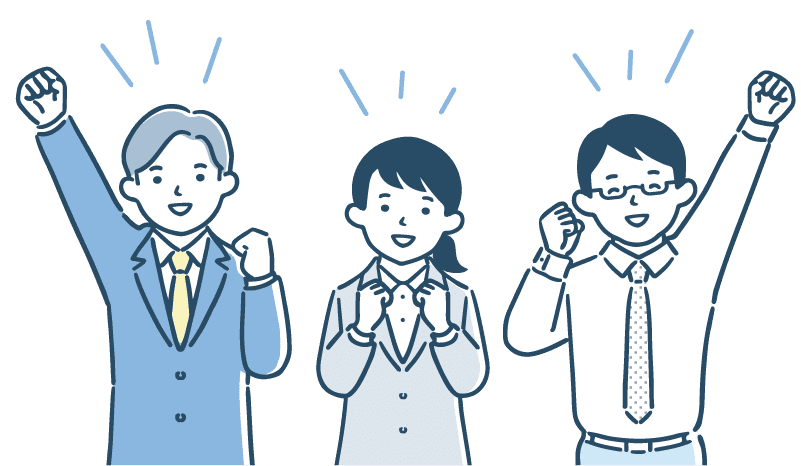1月29日、農福連携に取り組む峡東地域と甲府市の障がい者支援の施設を視察しました。農福連携は障がい者施設が農業者と業務委託契約を結び、施設が請け負った農作業の一部を施設に通う障がい者(施設の利用者)の方が行なうものです。農業者から作業料金を施設に支払い、それが利用者の方の工賃となります。こうした「施設外就労」に加え、最近では施設で独自に農産物を生産・加工・販売しているところも増えてきています。今回、伺った施設はいずれもこれらに取り組んでいます。(下の写真は)

自前でワインを醸造し販売も
視察した峡東地域の施設は、施設外就労で年間10件の契約があり、ブドウ、モモ、スモモなど果樹農家の仕事を請け負っています。果樹の出荷時期だけでなく、摘花・摘粒・剪定など年間を通じていろいろな作業を行なうことで、利用者の特性にあった作業が見つけられるそうです。この施設では農地を借り受けてブドウも栽培し、それを自前の醸造所でワインにして販売もしています。また、果樹をドライフルーツやジェラート、スムージーなどに加工して販売を行っています。(写真上:施設で管理するブドウ畑での作業の様子をうかがいました。写真下:ドライフルーツにしたブドウを袋詰めしている様子)

一方で課題も。収入源は加工品の販売収入と補助金ですが、販売は販路拡大をして商品を売らなければ収入にならないので、なかなか大量生産できないもとでは経営的に大変だそうです。こうした部分にも支援がほしいとのことでした。また、将来的には施設の利用者が、障がいがあっても施設での経験を活かして自営農家になってくれたらうれしいとも。そのためのサポートも必要ではないでしょうか。
農業分野で新たな可能性
もう一つの開所8年目となる甲府市の施設は、農福の補助金で施設を整備し、精神の方を中心に35名が登録、平均で20名ほどが通所しているそうです。平均年齢50~60歳。施設外就労ではリサイクル業、洗濯業など、農業以外の仕事も行なうそうです。生産加工販売ではジェラートや焼き芋を施設で加工し、店舗も設けて販売しています。ジェラートの材料はスモモ、ブドウ、モモ、イチゴ、お茶、くるみなど。主に農作業を行なう農家さんから分けていただいたものを活用しているそうです。また、焼き芋用のサツマイモは“ブランド”芋を仕入れて、施設内の焼き芋器で焼いています。ここでも加工品販売の収入では利益がなかなか出ないそうです。(写真下:くるみをジェラートに加工する工程について説明を受けました)

希望としては自前の農地を持ちたいそうですが、一つの施設だけで運営するのは大変なので、同じ意向のある複数の事業所で大きな畑を借りて共同運営するのが望ましいという考えをお聞きしました。その場合まとめ役や農業の指導をしてくれる専門家も必要になりますが、行政がJAなどとも連携してモデルケースをつくってみることも必要だと感じました。
山梨県では農福連携推進センターをつくり、障がい者支援施設と農家とのマッチングに取り組んでいます。先日もマッチング件数がここ3年間で、以前の2倍以上に増えていると新聞で取り上げられました。最初に話をうかがった施設では「農福連携を通じて、障がい者の方のために活動することはもちろん、農家の担い手不足や遊休農地の解消など、地域の課題解決にも取り組みたい」という声もお聞きしました。また、県内の障がい者支援施設では野菜などを生産して、特別支援学校の給食用に納品している事例もあります。農福連携の様々な可能性について、引き続き研究し提案していきたいと思います。